(1) 外形図について
外形図というのは文字通り、外形を表現する図面である。工業デザインの過程においては外形図によってデザイナーが意図したかたちをもっとも正確に伝えることができるので、プレゼンテーションとしての図面の中で一番重要なものであるといえよう。どんな精巧なモデルやレンダリングがあったとしても、ディテールにわたって正確なフォルムを検討し製作図に移っていくための基準としてこの外形図はなくてはならないものであり、そのためにはより正確にかたちのイメージを伝達するものでなければならない。多くの場合、外形図の描法としては機械製図にそって描いてよいが、かたちについて、より的確に把握していくためには省略ということに対しては細心の注意を払うべきである。たとえば、つまみ部分に切ってあるローレットや表面に出てくるビスの頭、リベットなどといった意外なものが、かたちを決定する時の重要なポイントになる場合がしばしばある。ある広さの平面があり、そこに止められた2本のクロームメッキで仕上げたビスの頭が、単調になりがちな平面を、緊張感のあふれた ダイナミックな面としてまとめあげている場合などというのはよく出会う例だと思う。これを機械製図の略画法に従って描いてみると、それらの部分が全休のかたちのバランスというなかで、どの程度の分量を持ち、強さを持っているか、あるいは、その部分の形状がはたしてその場所に適しているものなのだろうか等の大事な決定の段階での確認を図面を読む人の能力差などによって、あいまいなものをにしてしまうときがあり、モデルでは一応、納得していたつもりだったものが、生産された製品を見て、デザイナーの意図と製品との間に大きなへだたりがあったことを眼の前に見せつけられて、がくぜんとする場合もある。これは一つには、機械製図で規制きれた図法というものが、どちらかといえば、もののかたちの美しさを率直に表現しようとしているのではなく、ものをつくりやすくするためにいろいろな約束事をきめてあるので、小さなパーツなどについては略画法を使用することになっているので、結果的にはかたちに対する判断をしにくくしているといえる。いいかえれば機械製図は製作図を描くためのものでかたちを理解しようとする工業デザイン製図とは異なるものなのだということである。
もっともこのようなことが起こったとき、いえることは略画法云々よりも図面の描法や読図に対する経験、知識の浅さによることが多いということである。製図に対する正しい基礎を持たないままに応用を進めて行くと、白分勝手な独善的な図面しか描くことができなかったり、他人の描いた図面は読むことができないなどという人間を創ってしまう。が、当然デザイナーとしては、エンジニアサイドから送られてくる機構図その他の図面を正確に読み取れるだけの読図力が必要であり、あるいは自分の意図を相手にきちんと伝えられるだけの作図ができなくてはならない。また場合によってはデザイナーが自分で製作図まで描かなくてはならない場合すらあるのである。いいかえれば、機械製図をマスターした上に、更に工業デザインのための図面の描き方も身につけねばならないから、それだけよけいに勉強しなくてはいけなくなる。
機械製図法によってのみ、描いていくと、図面の表現のうえで納得できないところがずいぶんある。なかでも一番問題になるのはアール部分の表現方法であると思われる。
機械製図では曲面を表現するようなときにシルエットで捕えることができる外形のりんかくだけしか外形線(全線)で表現しないがこれではデザイナーのかたちに対するイメージを正確に伝達しているとはいえないし、かたちの検討という外形図の目的も遂行することは難かしい。
ここに数点、断面の外形を示した図面がある。それぞれ円形の石けん入れであるが、それらを機械製図に準じて描くと7図のように表現することができる。この上面図を見てもわかるように、機械製図では自分のイメージの伝達が読図の能力をしっかりと持った人にしかできない場合がでてくる。そのため、工業デザイン製図にはかたちをもっと感覚的にアピールできるような方法を考えねばならない。たとえばこの図に示した石けん入れの場合には、上面図に表われるアールの頂点心線でつなぐとよい。これを実際に描いて見ると8図のように表わせる。この中心線を1本描き入れることによって、もののかたちをはっきりと、正確に把握できるようになる。
この他にもアール部分がプラスのアールからマイナスのアールに変化するときには、その変曲点を捕えて実線の全線(外形線と同じ)で表わすとよい。これらの実例を二、三図示しておくので参考にしてほしい。
このとき、アールを表わす部分を表現するのに実線で示せる場合と実線を使わない場合とが当然でてくるが、使いわけというのは図形の大ききであるとか、ラインを入れたほうがかたちを把握するのに判読しやすいなどという、図面の見え方などから判断を下すとよい。しかし、この判断は簡単に下せるものではなく、かたちのイメージを完全に自分のものとしていなければならないし、いろいろな図面に対処して、その都度どういう判断をしたかという実績をつくっておく必要もある。いいかえればこうした部分の表現というのはデザイナーの態度、経験、感覚などといったものがそのまま表現に表われてくるものなので、方法さえ知っていれば誰にでもできるといったものではない。
外形図はかたちを最終的に決定していくための図面であるから、かたちに対する検討がもっともしやすい状態になっていることが望ましい。そのために図形の中には必要外の寸法数字、その他かたちを把握するために障害になるようなものは、いっさい記入してはならない。図形の外に入れる寸法等も、最大寸法など、最少限のものにとどめて、それも、図形からある程度離した位置に記入して、かたちに対して他の要素から影響を与えるようなことは極力避けるといった配慮が必要である。
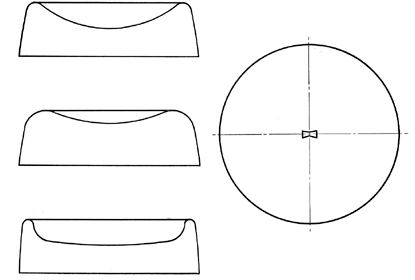
| 6図 | 石けん入れの断面図(肉厚は省略してある) | 7図 | 6図の三つの石けん入れの上面図を機械製図法ではこのように表 わす。 |
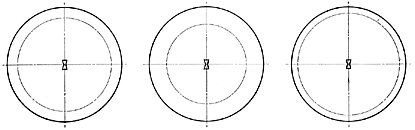
8図 各図形ともアールの頂点を中心線でつなぐことによりかたちの判断をしやすくなる。
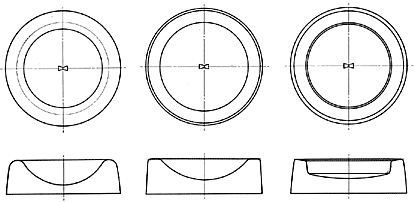
| 9図 | アールがプラスからマイナスに変る変曲点を求めて実線でつなぐとよい。 | 10図 | 角アールの部分は外形線を延長して交点を求め、その点を実線でつなぐとよい。 |
(2) かたちの検討について
外形図の目的は、かたちの検討とデザイナーのかたちに対するイメージの定着と伝達ということが主なことであるが、外形図という平面に描かれたもの、しかも数方向から見た図形を描き表わして、それを読む側が頭の中で組立てて、製品という立体のものを想定するというのはとてもむずかしいことである。全体のかたちは何となく理解できるが、ディテールがどうも読めないとか、逆に細部は分ったけれども全体のフォルムとの関連がちょっと把めない、などということもよくある。しかし、それも図面を読み取るという訓練を十分に積めば、一枚の図面からそのかたちということを理解できるし、部分と全体のバランス、つながりということも納得できるようになる。さらにはその図面からかたちの良い、悪いの判断さえも適確に行なえるようになるものである。ただし、外形図を見る対象のクライアント側の人が、全部がそうした読み取る能力があるとは限らないので、あまりそういう知識を持たない人でも読めるように親切に描いておくというのはいいことであり、そうした描き方をした図面というのは結局自分にとってもかたちを検討しやすい図面ということになるのである。たとえば角アールにしても、図面に描き表わすことによって、よりシビアに感じとることができるし、自分のイメージの定着もできるわけである。各部の関係や面の持つ表情といったものも、作り勝手などと同時に、こうした図面で精密に検討されて決定されるものである。角アールを2mmから3mmに変更したら製品の表情が柔らかくなったので、他のものにそれを応用したら、だらしなく、間のびしてしまったとか、円筒形は図面に表わしたときは、実物より2割かた、大きくみえるなどといったこともわかってくる。そうした各部の処理まで詳細に検討した結果を最終的に正しく描き表わした図面に仕上げるということで、かたちの検討、決定、定着というデザインのプロセスでの最終段階が、ほぼ終了したことになる。