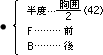前述のことを前提にラグラン袖の作図実験に入る。袖山5段階に適合する、身頃原型を作図し、その袖刳寸法を測って、それに適合する5段階のセットインスリーブを作図する。尚図8のように身頃ラグラン線のパターンを作る。
A、袖落度の測定
袖山つけ寸法と身頃袖刳寸法の差の分(いせ量)だけ、袖山中央線より離して図9のように、袖山高1/2で身頃袖刳と接合させて据える。前身頃1/24半度の位置では0.5cm程度重なることになるが、身頃1/24半度の位置は体幹と腕との分れる腋点と考えられているが、作図上の位置は下がっているため高い位置での接点で適当と思われる。後身頃も前と同様に袖山高1/2で身頃刳と接合するように据える。
袖落度の測り方は、図9のように肩線を延長させ、袖山中央線との交点を基点として測った。
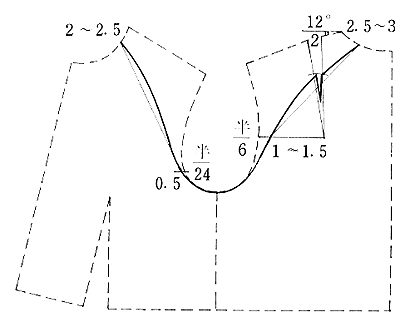 |
| 図9 |
袖落度は袖山の高い、運動量の少ない袖ほど強くなり、袖山の低い袖は少なくなる。図10の表は実験した袖落度表で、図11はその比較図である。(ブラウス原型使用による)
袖落度の強い袖ほど、袖巾が狭く肩ぐせが多く静的な袖となり、袖落度の甘い袖は袖巾も広く、袖下も長くなり動的な袖になる。肩ぐせも少なくなり肩線をわにつづけて裁断することも可能になる。(31頁21図参照)
B、袖落度の前後差
袖山の高い袖ほど差が多くなり、袖山の低い袖は前後差なしになった。つまり袖山の低い袖のばあい、袖落度は同じで肩落度の差だけつくことになる。
C、腕の厚径分
セットインスリーブのばあい、袖山のいせ込みによって厚み分がでる、変型袖のばあい袖と身頃がひと続きに裁断されるので、そのテクニックは活用できないので、作図の時に厚み分だけ肩線を延長して、そこから袖落度をとり、腕の厚み分を出す方法をとっているが、実験の結果基準となる、袖山の高さに対する、厚み寸法が算出された。(図12)
袖山中点から袖落度を測った基点までの長さで、袖山の高い袖落度の強い袖ほど多く厚み分が必要となり、据りの甘い袖山の低い袖ほど少なくてよい事が実証された。
この寸法は肩線のシルエットを描き出すためのものでもあり、デザインや体型によって基準寸法を固守せず自由に変えて表現する事も可能である。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
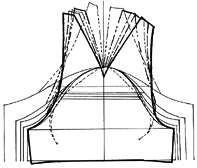 |
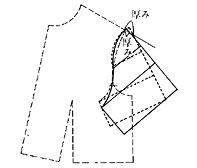 |
|
| 図11 | 図12 |
7、袖落度活用について
10図表は、実験の結果であるが、パターンのわずかな誤差やおき方によって、度数はかなりの動きが認められる。このばあい何度か同じ実験を繰返えし、その平均度数を現わした。
前後袖落度差は活用にあたり、動作範囲を考慮し、後屈より前屈動作による背部伸展の適合が衣服の構成上必要なので、運動量を含めて、前後差を標準5°として実験することにした。同率5°にすることによって袖山の低い袖ほど運動量が多く入る事になる。
作図にあたり実験で得られた前袖落度より5°マイナスした度数を後袖落度にした。図13のように肩線を延長し、厚み分をだした点を基点とし、袖落度をもとめて袖のパターンを図のように写すと作図が簡単にできる。
後身頃は背巾線位置で袖との間に空間が生ずるが、この分量が背巾の運動量にプラスされ、袖のわたり巾に含まれる結果となる。
標準差を5°にしたが、造る衣服の性格や種類、用途等によって、機能面から更に運動量を必要とするばあいや、感覚的に背部にボリュームのあるドレープがほしい時などは、前後差を10°または、それ以上つけ後袖の据りだけ甘くする。このばあい袖のパターンを据えてみると、背巾線での空間が多くなり、運動量またはドレープ量の増量が平面作図上でも把握できる。(図14・写7参照)
後袖のわたり幅が広くなるが、ラグランスリーブのばあい美的感覚を減じないのが、この袖の大きな特徴でもある。
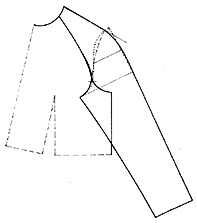 |
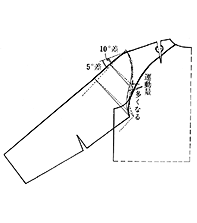 |
|
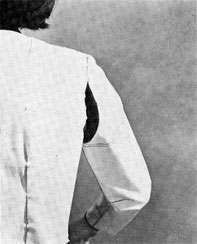 |
8、体型による袖落度
肩落度の差異は、僧帽筋が肩のカーブを決定するといわれているが、鎖骨の伸びも影響して、怒り肩やなで肩の体型の人が意外に多い。変型袖のばあい前述の如く肩線が袖の方向を決定する重要なポイントになるので、肩落度差による袖落度を実験することにした。
A、なで肩
実験段階として肩線を補正した原型に、標準の袖落度を取り、袖のパターンをのせてみると、図15の如く前後とも、袖山高の1/2で身頃との重なりが多くなり、袖のわたり巾が標準より狭くなることが確認された。
図15は標準体との比較図である。袖の点線がなで肩、細い実線が標準体で袖わたり巾の差が目立つ、これでは袖落度が強すぎる結果がでたので、6の実験段階と同様に、袖パターンを袖山高の1/2で身頃袖刳と接合させて図16のように据えて、袖落度を測定すると、この方法のばあい標準との肩落度差を標準袖落度からマイナスした度数と前袖落度は一致をみ、後は更に2°甘くなった。
この方法を学生にも実験させた結果、仮縫いでの補正が少なく適切であることが確認された。また図16カットの如く肩線からの腕シルエットをみても標準袖落度より少なくなることが適当と思われる。
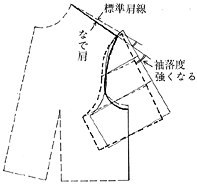 |
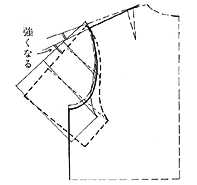 |
|
| 図15 | ||
| なで肩 | ||
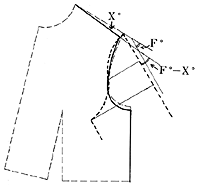 |
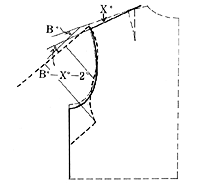 |
|
| 図16 | ||
| 怒り肩 | ||
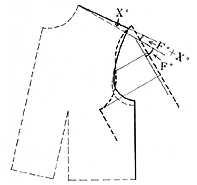 |
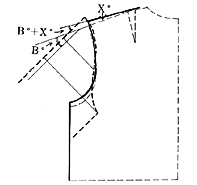 |
|
| 図17 | ||
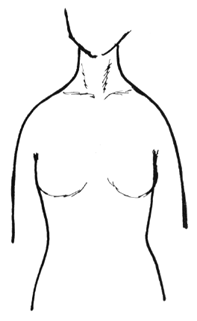 |
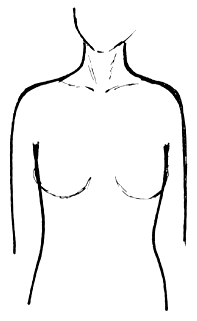 |
|
| 図16-2 | 図17-2 |
B、怒り肩
身頃原型の肩落度を上げて訂正し、なで肩と同じように袖パターンをのせて袖落度を測定した。なで肩とは逆に標準との肩落度差を標準袖落度にプラスした度数と前後とも−致した。図17参照、つまり怒り肩のばあいは袖落度が強くなり、なで肩のばあいは標準より甘くなる。
C、前肩
最近若い人に多くみられる体型で、上腕骨頭が前よりになり、肩の前側が凹み、つまり大鎖骨上窩が強く、更に上腕骨頭が前よりになるので、肩胛骨の張りが目立つ体型である。
原型は肩線を前よりに移動し、肩ダーツ量も増す、肩落度は前が強くなり後は甘くなる。前後肩落度差は多くなるが、出来上り肩落度は変らない。
袖落度は前は「なで肩」後は「怒り肩」と同じ補正をする。つまり前袖落度は標準より甘く、後袖落度は強くなる、肩度と逆の補落正になるが、出来上り袖落度は肩と同じように変らない。