

| 「ICSID'75 MOSCOW」と東ヨーロッパの インダストリアルデザインの視察報告 金子 至 |
PAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
 |
 |
|
| 6000室もあるホテル・ロシア、中央が会場入口。 | 会場左、ICSID幹部席。 |
| 開会式会場のレイアウトは、正面に細長いスクリーンを置き、特別につくられたこれも細長い白い陶器の花瓶が三々五々舞台前面に置かれ、短く花が差されている。舞台左側にはICSIDの会議執行の幹部、右側は新聞記者席になっている。発言者の演壇は向って左の袖の部分にかかる。照明は小型のシャンデリア─この国の公共建築の基準であるかのような─とスポットライトである。 定刻10時、ICSID会長カール・オーバック グビシアーニ氏の挨拶の主旨は、「資本主義国の経済発展はいろいろの問題を生んだ。われわれの計画は、人間の生活に根ざし、物質主義ではなく、精神的な問題を加えながら、インターディシプリーナリー(学際)の時代であり、真に人間のために考えるようになってきた。昨年ブレジネフ氏は同じように述べていたが、私は共感している。全ソインダストリアルデザイン研究所(VINITE)は9支部をもっており、現在約4,000名のインダストリアルデザイナーがわが国で活躍している。その所長はソロビエフ氏である。今後この様な考え方で行うならば、インダストリアルデザインは必ずよい時代をむかえるであろう。また社会主義国のデザインも発展するであろう。」 ユーリ・ソロビエフ氏の"デザインと国家政策"DESIGN AND STATE POLICYの基調講演の要旨は、「全ソインダストリアルデザイン研究所は1962年に開設された。社会主義国で強力なデザイン団体としてその成果をあげている。社会主義国では科学をデザインの基本として考えている。ソ連では科学技術委員会と共に、10年前からさらにデザインの質を高める方向をとった。最近その実績が上っている。東ドイツのデザイン組織とも情報交換を互に行っている大変親しい間柄にある。現在社会主義国では、国がデザインのクライアントになって、デザイナーおよぴメーカーを通じオーダーをすることも行われている。資本主義国の無駄は、ヨーロッパにおいて、ハンマーが500種もあり、アメリカではさらに多くのものが市場にある。テレビキャビネットは、オランダで調査したが、これも約500種にのぽっていることが解っている。これは社会主義国では考えられない。ステートポリシーとしては、スタンダードを決め、質を高めていきたい。 第二のテーマ"デザインと科学"DESIGN AND SCIENCEが終って昼食である。この東側の昼食はどの国でも2時からである。立式のテーブルはさすがに高い、私の胸のあたりである。種類、量とも多く、豊富であるが、列をつくらなければならない。ソ連ではぜいたくな食事であろう。質はよい。 |
 |
 |
|
| 会議場。 | 会議用カバン(東独製)。 |
| プログラムによると午後の会議に続いて、同じ会場で夜8時から11時半までがコンサートとなっている。しかし実際は多彩なプログラムであった。前半はヨーロッパからの導入の音楽、後半はロシアの民族音楽である。その前半はまず、5人のバレリーナの典型的なロシアバレー(優等生的でもある)のコッペリアから始まり、マンチエコフのバリトン、タマラシナスカヤのソプラノの間に再び10代のパプロバによるバレーのデュエットがあった。これはこのコンサートの中で、最も賞賛に価いするものであった。優雅さとその態度に気品が満ち溢れていた。はたして、各国のデザイナー達の盛んな拍手があった。彼女はそのために3度も舞台から心をこめた返礼をした。彼女はあのアンナ・パプロバの一家であろうか、そうだとすればバレーは伝統をふまえる世襲制度であろうかと考える。ソ連のバレー界の次代をになうのは彼女であることは後になって知らされた。この一幕で本日の資本主義国をせめる演説など遠くにふき消されてしまった。 |
 |
| 分科会、左からブルークハウト(西ドイツ)ケルム(東ドイツAIF所長)、一人おいてシュミット(東ドイツAIF副所長、クレソニエル(ベルギーICSID事務総長)。 |
後半の民族音楽と舞踊は、発声法の違う超人間的なボリュームのバスやテノールで、さながら40cmスピーカーの前にいるようであった。そしてコサックのあの激しい跳躍が続いた。われわれはこのあと12時近くにホテルのロビーで、本日のコングレスに対する評価のために集まった。そして本日の会議の発言者の中から主要な語を抜粋してみると
また午後の発言は分科会に別れたパネルディスカッションで、チェアマン2名を含め、7名から10名の構成である。その中に日本のJIDAから4名のパネリストが加わっている。分科会は前述の2つのテーマを受けている。
ディスカッションは必ずしも明快な結論が出るわけではない。それぞれの感想を拾ってみると、「ステートポリシーについて、西独は整然と行っているといってよい。カナダ、オーストラリアもそれなりのポリシーをもっている。しかしソ連のように決定的なきめられ方を押し出しても、それぞれの国によって考え方が違っていいはずである。国の母体が違うが、スエーデンの発言で─ものつくりに消費者を参加させているが、必しもうまくいっていない。実行はしているが他に何かいい方法がないか─という質問もあった。」結局第1日目の会議の印象は、同じ語彙を使いながら壮大な話が多く、自由主義国に対するデザインの軋 |
| モスクワとデザイン ●ソ連におけるインダストリアルデザインは、科学的な側面と芸術的側面の両面を含んでいる。デザインは生態的バランスをとって生活環境をつくり出し、さらに科学技術を有効に役立て、デザインに結集し、社会的な種々の問題点に立ち向って解決を与えていく。それはインダストリアルデザイナーにとって義務である。というステートポリシーの論旨は理解できるものである。しかしその論旨の発展が、具体的に実体としてこの5日間のモスクワ滞在で発見できるであろうか。私の興味は会議よりそのことに集中していった。特に今回の会議は、ともすると建前論であって、本音を示さないところに疑問を残していたからである。 まず街に出て見ることを第一に、つぎはソ連の家庭を見ることができれば、という計画である。しかし後者は非常に困難であろう。街といっても、月並な観光コースではない。私は人為的とも思える観光は好まない。記念碑的な拡大された内容は、それが事実であっても、その人為的な匂いは見方を歪ませてしまうからである。私は観光土産品というものを今まで買ったことがない。特別に若い女性のニーナに市内の案内を頼んで歩いてもらった。そして私の質問だけに答えてもらうようにした。時間の都合もあって、地下鉄は革命広場からキエーフスカヤまでを折返して、グム百貨店を見るまでで別れなければならなかった。 地下鉄の駅は、ホテルよリ一段と光量が不足していた。長いエスカレーターは日本の1.5倍位の速さで、荒い鉄の桟の上に乗せられているようであった。右側に寄り、左側はかけこみの人のためにあけておくのがルールである。大理石のフォームはステートポリシー以前である。全線8路線138.2km、全線20K(カペイカ─約60円)、車輌はすでに経年変化で、エアサスペンションの車輌になれた私は、踵に直接細かな振動が伝わってくる。むしろ後に訪れたチェコのプラハの地下鉄の車輌─ソ連の新技術導入によって昨年3月開通した─の方がはるかによいものであった。勿論これは日本でも同じことで、東京の場合でも一番古い銀座線にもあてはまるものであろう。 ものの見方はなかなか客観的になれない。判断はともすると日本の現状との比較論に終止してしまう。つとめてこの国のこの人達のために、その道具が適切であるかどうかという評価をしなければならない。 |
 |
| 赤の広場とグム百貨店。 |
| グム百貨店は、クレムリン宮殿と赤の広場をはさんで対面している。革命前に200ほどの小商店があったが1953年に改造され、内部は細かく仕切られた、それぞれ専門店に分かれている。寄り合い商店街であるから、全部を見ると約2K半はある。商品が少ないわけではないが、種類が少ない。売子が少ないせいもあって買物は列をつくってしまう。一つは買うものの伝票を書き、その伝票をレジにもっていって受領書をもらい、その受領書を示してはじめて品物が手に入るというシステムになっているところが多いので、いきおい時間がかかるのである。ソ連のデザインは一見したところ、生活用具にまで及んでいないという印象をうけた。ソ連の計画経済は、当然公共デザインを優先しているであろうから。だが、バス、トロリーバス、路面電車に見られる公共デザインも、決してステートポリシーから考えられたものとも思えない。乗用車はジグリ(イタリアのフィアットと提携)ボルガ、モスコビッチ、サポロージェ、チャイカ、ジル(高級車)がある。一昨年モスコビッチをアメリカのレイモンド・ローウィRaymond Loewy(注5)にデザインを依頼したというニュースがあった。デザイン料は、アメリカ80%、ソ連20%という。一見不可解に思える。 |
 |
 |
|
| ソ連製乗用車。 | ジグリ。イタリアのフィアットと提携。 |
|
 |
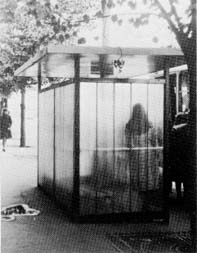 |
|
| 清涼飲料クワスの自動販売機。 | バス・ターミナル。 |
|