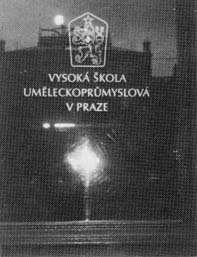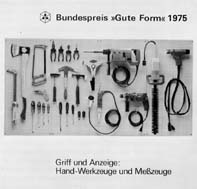●クラコウから夜行の国際列車で東ベルリンに着く。東独デザイン庁Amt
「ドイツ民主主義共和国は、国家政策としてインダストリアルデザインを取入れている。国がデザインを発展させるための要求をわれわれに出している。われわれはそれを受けて、公共・人民工場等を通じて指導管理する義務がある。工場によって計画的にデザイナーを配したりする。例えば1976年〜90年にかけて何人のデザイナーを雇用せよという要求をする。デザインはすべての問題の中で質のコントロールを正しくするために有効性がある。国がものの質をコントロールするために必要なのがデザインである。われわれは国の閣僚評議会にわれわれの決定した提案を行う。それには実践した分析に基づいて、そのものが発展段階をとっているかどうか、国際的なものとの比較はどうかの認識の中から決定へともっていく。最終的には閣僚評議会が、国家的なレベルで管理コントロールをそれによって行う。私は目下、ファッションに決定的な分析を行っている。靴や新しい食器にどうファッションデザインとして発展させるべきかである。これも決論が出れば提案の形をとる。また工場へも分析結果を伝える。
将来インダストリアルデザインの発展をどのような方法で考えるか、デザイン領域の拡大の問題、デザイナーの数の要求と、再教育の問題が課題となっている。
研究所の構成は3部門にわかれ、労働環境の形成、または技術をコントロールする部門、第2に消費部門との関係、第3に国際部となっている。この協会とは別にデザインの教育については、専門校が2つある。東ベルリン大学には芸術学部の中にある。またモードデザイン研究所があって、約400名が可動されている。そこでは衣料、靴からカバンにいたるモードの生産体系までたてる。ファッションはスタイリングではないし、スタイリングには私は反対している。勿論10年間も同じものがよいというのは間違っているし、人間の心理学的な決論を待つが、心理的に一番よいと思う方法を把えることである。毎年スタイリングを変えようとは思わない。閣僚評議会の組織は各省を包含しているが、その中で文化省、工業省だけでなく文部省とも関連がある。評議会第一副議長は私の上にある。デザイン学生は毎年40名が社会に出るが、数は不足している。これを80名に増やすためには、文部省、文化省に提案要求をすることになる。デザイナー再教育は重要な課題であるといったが、現在ゼミナールで2週〜4週の学習を行い、またアイデアの会議を行っているが満足していない。将来はデザイナー再教育のためのアカデミーをつくりたいと思っているが、現在は器の教室がないので1〜2年の間にまず第一形体をつくるようになるであろう。ドイツに住む外人デザイナーとの提携交換もあって、自動洗濯機や医療機械を協同でデザイン開発している。」
以上が私の未整理のままのケルム所長の話であった。スライドは東ベルリンの紹介のあと、ペーターベーレンスの1925年の照明器具のデザインから始まったことは印象的であった。質問の中で資源に乏しい両国の共通点が語られたりしたが、東ドイツの人口1,700万人に対して、日本は1億1千万だから、より日本は輸出が重要であることや、環境問題とデザインの係わり合いについての話もあった。シュミットWolfgang Schmidt副所長の質問で、日本はエンジニアとデザイナーのパーセンテージはどの位かという点については、企業の例をひいて答えてもらった。
東ベルリン芸術高等学校とプラハの工芸学校
●東ベルリンの郊外に近い静かな地区にあるこの芸術高等学校は、中庭をはさんだ校舎の左がデザイン科である。清潔な引締った感じの二階の研究室に、第1学年の担当のプロフェッサー・コーン女史を訪れる。すっきりとした品位のあるしかも礼儀正しい女性である。1学年は技術と構成で手の技術のみで課題に対して自由な発想のセンシブルな構成をつくらせている。「その点、日本の完成されたデザイン教育を模範にしている。デザイナー教育はセンシブルでなければいけない。自分の考えついた形を、手の言葉として始め、理論的なものは後期に行う。分科するためにあまり時間はないけれど。色彩については9色の配合を基準にして集中した学習をしている。2年はエンジニアデザイン(ID)の方向と、他のデザイン部門に分れる。第3学年は、それぞれ具体的な制作にかかる。国からの命令を受けて産学協同の制作である。学生数は3学年のデザイン科は60名、教師は4名で、毎年12名のIDデザイナーが卒業していく。しかしこれを20名にしたいが、残念ながら教室がないのが現状である。学生中50%が女性であって、IDのような厳しい職場に対して訓練をもっと行いたい。」私は彼女の背後にある陳列ケースの参考作品を見せて欲しいと断ってハンカチーフで手にしてみた。センシブルといった言菓のとおり、石膏の作品の表面は艶やかに光沢があり、どれもが1.5mm程の厚みで透きとおるように、きわめて精度の高い緻密な仕上をもった作品群であった。ここの学生は材質感の精度を知っている。そして精度を手中におさめている。この精度は内容を表現するのにきわめて役立った造形を見せていた。